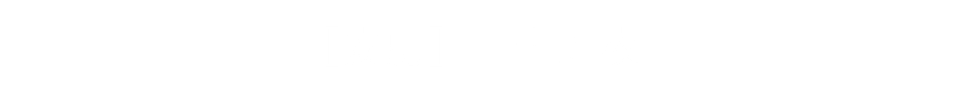十五夜
概要
・九州中部以南で広く行われる旧暦8月15夜の綱引きだが、屋久島では各集落で綱の作り方から綱引きの様式まで様々である。
・昭和30年代後半までは9月13夜にも綱引きが行われていたというが今現在すたれている。
・過去の記録を見ると行事の様式は変化しているのが読み解け、また現在行事を主導している人たちにも高齢化が目立ち、伝統の後継が不安視される。
平成28年9月11日{縄ない}の記録
・午前8:00頃から簡易的な櫓に掛けたカズラを編み、カヤを絡め始める。
この日以前からカズラやカヤを集める作業がなされており、早めに来て算段をつける人と9時ごろから集まってくる人たちがいた。
・始終櫓を利用して縄を作ってゆくのが安房区の特色。
カヤに混ざったススキを抜き、切りそろえてカズラに編み込んでゆく。
・雨にせかされるように昼前には編みあがりビニールシートで覆って15夜の日を待つ。
平成28年9月15日 一五夜の記録
・夕方六時前頃人があるまってくる。公民館前にはススキと焼酎とおはぎのお供え物が用意される。
・縄を丁度良い位置に据えられたら一五夜の歌を歌う。~~「東西東西・・ヤッ」
繰り返し三度歌えば「わっしょい{わっしょい}」の掛け声で里町方面へと皆で縄を担いで走り出す。
・縄が丁度竜がうねりながら進むように、蛇行して走る。若宮神社前で縄を置き、お参り。
・再度一五夜の歌を経て走り出し、今度は如竹廟まで移動、綱引きへと移行。
・〇綱引き歌。各集落{小組合}や大人と子供等に分かれて綱を引く。かつては綱が切れるまで行ったというが、今は途中で鎌を用いて縄を真ん中で断ち切る。
・切れれば今度はそれを如竹廟内へ運び相撲大会。参加した子供はお菓子が貰える。
・八時半前には解散。土俵の片づけは後日。
【参考文献】
屋久町郷土誌第3巻・4巻
写真
安房市街を縄担ぎ駆ける
安房市街を縄担ぎ駆ける。 |
安房は櫓を使う
安房は櫓に蔓をかけて縄をなう。 |
蔓の結び方
蔓の結び方 |
ひもで束ねる
ビニールひもで束ねる |
蔓を延長する。
蔓を延長する。 |
萱を加え結ぶ。
萱を加え結ぶ。 |
太い綱が出来てゆく。
場所により太い物が出来てゆく。 |
例年の記憶を辿る
あぁでもない、こうでもない。 |
雨が降り始めた。
雨が降り始めたが止められない。 |
3方向に分けて紡ぐ。
3方向に分けて紡ぐ。 |
力技。
力技。 |
萱を切りそろえる。
萱を切りそろえる。 |
ススキが混ざる。
ちょくちょくススキが混ざる。 |
雨除けにビニールシート。
完成後雨除けにビニールシート。 |
一五夜当日、開始前。
一五夜当日、開始前。 |
おはぎと供え物。
ふるまいのおはぎと供え物。 |
歌を三回繰り返す。
一五夜の歌。三回繰り返す。 |
回目でだっと駆け出す。
舞台演芸 和太鼓 |
若者総出。
若者総出。 |
高身長は負担が大きい。
高身長は負担が大きい。 |
若宮神社お参り
若宮神社お参り |
月下の若宮神社前。
月下の若宮神社前。 |
如竹廟に向け出発。
今度は如竹廟に向け出発。 |
如竹廟前に到着
舞台演芸 よさこい |
集落対抗綱引き。
集落対抗綱引き。 |
切れたら土俵づくり
綱が切れたら土俵づくり |
相撲を取る。
相撲を取る。 |
つては月明りだったのか。
かつては月明りだったのか。 |
解散後の土俵。
解散後の土俵。 |