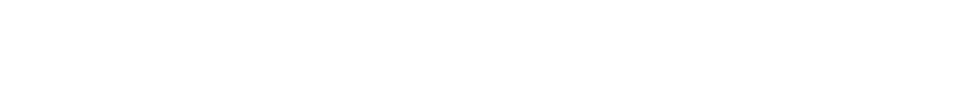安房川とその周辺
概要
・屋久島四大河川の中の一つとされ、中でも最大の流域面積を誇る島内最大の川。
最高峰宮之浦岳に源を発し、総延長20Km程で海へと下る二級河川。上流域は現在世界遺産地域や屋久島国立公園に指定される原生林を擁し、その森の豊かさは永らく人々に富をもたらしてきた。
・上流部にはかつて木材の一大生産拠点として栄えた小杉谷を擁し、その伐採の為の森林軌道はこの川に沿って安房の港まで下りてきていた。豊富な水量と高低差は屋久島全域に電気を供給する発電事業に利用され、その森林軌道は今も発電所の管理の為現役で利用され続けており、日本で唯一現存する森林軌道として経済産業省の指定留守日本近代化産業遺産に指定されている。
・河口近くの汽水域では近年、カヌー・SUPツアーが人気を博し、屋久島観光の中ではすでに重要な位置づけとなってきており、屋形船による「流し船」{→リンク}等が盛んにおこなわれている。
・自然のみならず文化・歴史の面からも語ることの多い、重要な存在といえる。
〇大石亀女の岩
・里町の河岸に、亀女という女性がその上で機織りをしたという花崗岩の岩が存在する。
・その後大岩は浸食によってか護岸から離れ、近年の護岸工事により再度つくまでは泳いで行く以外無い程離れていたという。{地元民聞き取り・設置看板}
〇伊能忠敬上陸地
・特に石碑等は作られてはいないが、記録によると文化9{1812}年3月27日夜10時頃、伊能忠敬を隊長とする幕府の測量隊19人、薩摩藩の屋久島種子島測量着添い役並人歩160人余りの合計180人余りが安房の港に入ってきた。
・内91人が里町の善蔵・幸八・善次郎の三宅に分宿し、測量ののち4月の14日再度宿泊に来たとされる。
・測量隊の屋久島滞在28日中17日が安房であったという記録から、測量の拠点として成功に大きく寄与したと言える。{資料・郷土史3巻30頁以降}
〇面影の水
・安房川橋のたもと右岸側、通称唐船渕とよばれる河岸にそそぐ湧き水。
・昭和30年代の道路拡張工事で大きく姿を変えてはいるが昭和20年代に水道が発達するまで、生活に必要な水を供給する重要な水源であった。
・乙姫{豊玉姫}が山幸彦と出会った場所とされる。{資料・設置看板}
〇発電所
・屋久島の電力事情の根幹を支えるのはこの安房川水系の発電所郡となる。
・安房川千尋滝発電所{昭和28{1953}年完成}安房川第一発電所{昭和35{1960}年完成}安房川第二発電所{昭和54{1979}年完成}、付随して上流部に尾立{荒川タ}ダム、下流汽水域に放水施設がある。
〇中州
・集落から安房川を遡ると、しばらく穏やかな汽水域が続き、発電所の放水口の正面に砂で出来た中州状の場所があり、共同墓地付近から歩いて/車でアクセスすることも可能であるが、現状カヌーツアーがよく立ち寄る場所となっている。
〇上流域
・安房川を遡ればヤクスギランド、淀川{淀川小屋}、小杉谷集落跡地・縄文杉等屋久島を代表する景勝地の多くへと行きつく。