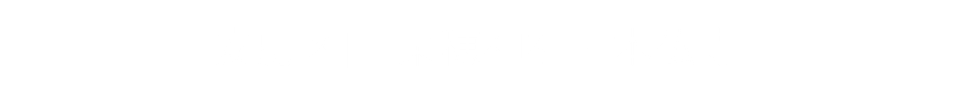粟穂神社・本仏寺
概要
〇粟穂神社
御神体 鏡二面が社内部に鎮座。
祭 神 正祀 天津日高彦彦火火出見尊
相殿 ??草葺不合尊{うがやふきあえずのみこと}・大山祇命・金山彦命 配祀 屋船久々能知神・屋船豊受姫神{夫婦 家の神様}
牛置帆負神・彦挟知神{夫婦 大工の神様}
祭日 陰暦三月三日/陰暦九月二九日
・その他情報 創始は全くの不明、明治の時代の廃仏毀釈により僧侶の管理であったものが神道一色に変わったとされる。戦中は出征兵士の武運長久・願ほどきに多くが参 詣したが、近年は静か。
・拝殿横には元々如竹神社横に祭られていたという石碑軍「浜の神」が祭られて いる。
同敷地と呼べる隣に本仏寺があり、神仏混交の面影を感じる。
〇本仏寺
・京都本能寺尼ヶ崎本興寺の末寺。律宗であった種子・口永良部・屋久島は、長享二年{1488}に全島法華経に帰依し、本能寺・本興寺第七世日像聖人の開基とされる。
・本仏寺の元に本要寺{船行}・本慶寺{麦生}・本院寺{原}・本経寺{尾の間}・ 典良院{小島}などを置き、その中心的存在であった。日章こと泊如竹を産んだ寺である。
・構内には泊如竹の作ったとされる用水路「如竹堀」、第二次大戦戦没者慰霊等があり、粟穂神社の大祭に合わせて慰霊祭が行われる。 昭和五二~五六年の四か年事業で安房霊園に移設されたが、かつては裏手に霊園があり、歴代住職の墓も存在した。
【位置的情報】 安房集落を見下ろす丘の上、神社仏閣にありがちな一等地に本仏寺・粟穂神
社ともに並んで存在する。
【文献・資料】 文献1 屋久島郷土誌第三巻 P355前後