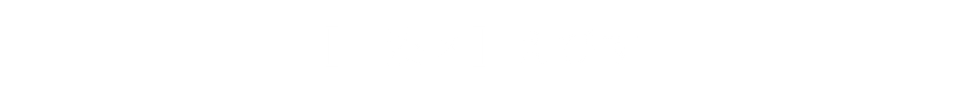えびす
概要
町恵比寿神
・江戸時代後期、向江町に新設(旧青年館横)。
・戦後、公民館完成後に現漁村センター前に安置。
・昭和40年一湊川支流(現ガジュマル通り)埋め立て時に、川から出てきた水神様と一緒に病院横に安置していた。
・風雨に晒され、ご神体の腐食が激しく、前安置場所で供養・焼却し、屋久杉で新調した。
・小倉末八区会議長(当時)が屋久杉を寄贈、大工寺田春吉氏の作。
・平成20年(2008)にガジュマル通りに鳥居を設け、水神様と一緒に移転した。
浜恵比寿神
・設置時期は定かでないが、カツオ漁の盛んな江戸時代にはあったと思われる。
・旧漁協(公民館前横駐車場あたり)の前と、河口の船が出入りする(現在の)あたりにあった。
・石の祠と魚を抱いた石造り。
・4月1日にエビス祭り(浜でばい)6月3日に漁祭り(みなと祭)をしていた。
・「ナンマンそうろ」で餅を投げ込む。
・相撲をとって奉納。
・現在、7月海の日の前の日曜に「一湊浜まつり」として両方を一緒に開催している。
海の祭り エビス様信仰
・屋久島のエビス様信仰には二系統あり。
・魚を抱いた像をかたどったエビス様(カツオ)と自然石(トビウオ)を祀ったエビス様
・一湊中心で 船玉様は女性の神様で女性が一名で船に乗ると遭難するので二名以上で乗る。
・一名で乗る時は人形を抱いて乗ると良い。
・エビス様を子供達が竿でつついたりいたずらすると祟りで漁がなくなるとされている。
・海の流れ仏(漂流する遺体)もエビス様と呼び、これにぶつかる船はマンがいいと喜ぶ。
【文献・資料】
・一湊百年
・一湊町歩き資料
・上屋久郷土誌